『交雑する人類』デイヴィッド・ライク ― 2019-02-13

足が長く見える
『交雑する人類 古代DNAが解き明かす新サピエンス史』デイヴィッド・ライク (日向 やよい 訳 NHK出版)
![]()
2月13日
『交雑する人類 古代DNAが解き明かす新サピエンス史』 | NHK出版 読了。
2月13日
『交雑する人類 古代DNAが解き明かす新サピエンス史』 デイヴィッド・ライク 読了。
タイトル通り、とにかく人類は移動に次ぐ移動で交雑に次ぐ交雑を繰り返したことが古代DNAと現代人のDNAを解析する事で明らかになっていくスリル。
これを合わせて読むと大吉。
twitter.com/march_hare_bro/status/1061224199723741189?s=19…
2月13日
第三部は、人種差は虚構で個人差があるだけだという近年のドグマと、ゲノム解析で明らかになってきた集団の系統を拡大解釈したナイーブな人種主義の復活の両方を批判する所信表明ですが、『ゲノムで社会の謎を解く』ダルトン・コンリー&ジェイソン・フレッチャーを読めばさらに難しい問題が露わに。
『ダーウィンの危険な思想』ポダニエル・C・デネット ― 2018-12-10

デジカメテスト中。夕景モードのこたつ猫
『ダーウィンの危険な思想
-生命の意味と進化-』ポダニエル・C・デネット (山口 泰司、大崎 博、斎藤 孝、石川 幹人、久保田 俊彦 訳 青土社)
![]()
5月14日
んで、あんまり頭にきたので、ポイントつかないけどYBCではいつも置いていない、デネットの『ダーウィンの危険な思想』を丸善でぽーんと買ってきたのよ。「デネット、面白いよ」とこないだのツイートしながら、この主著を読んでないのもまあ無責任だし、そもそも読みたいから。
11月13日
第2章まで終わったが、あんまり目新しいことがない。前提の確認を入念にやってるんであろう。しかし、大陸系の悪意の文章に比べて実に読みやすい。
11月15日
「歴史的不可能性では、単に取り逃した機会が問題になっているだけである。私たちの多くがバリー・ゴールドウォーター大統領誕生の可能性について心配する時期があったが、実際にはそれは起こらないで、1964年以後は、それが起こりそうもない見込みが長く続いて私たちを安心させてくれた」 半世紀で…
12月4日
やっと、第三部。グールドをやっつけて返す刀でチョムスキーを袈裟切り中。
12月10日
『ダーウィンの危険な思想 生命の意味と進化』ダニエル・C・デネット 読了。訳者あとがきがぐしゃぐしゃだった。徳性を論じた最終盤以外は極めてまっとうなデネット。時代的に二重過程モデルが出てくるのはこのあとか。私はどうしてもデネットの動物と人間をジーンで繋ぎミームで分断する手口に眉唾。
12月10日
この本だけでは、ミームはなんて使い勝手のいい万能酸だろう、としか読めない。
![]()
『ダーウィンの危険な思想
-生命の意味と進化-』ポダニエル・C・デネット (山口 泰司、大崎 博、斎藤 孝、石川 幹人、久保田 俊彦 訳 青土社)
『ゲノムで社会の謎を解く』ダルトン・コンリー&ジェイソン・フレッチャー ― 2018-11-10

線分の長さが各々の遺伝子的距離ね。
『ゲノムで社会の謎を解く
教育・所得格差から人種問題、国家の盛衰まで』ダルトン・コンリー&ジェイソン・フレッチャー (松浦 俊輔 訳作品社)
![]()
10月29日
そんなわけで今年もあとわずか。進化とか遺伝とか関係で枕元が危ないので、まずはこれを。
『ゲノムで社会の謎を解く――教育・所得格差から人種問題、国家の盛衰まで』ダルトン・コンリー&ジェイソン・フレッチャー
http://www.sakuhinsha.com/politics/26771.html…
https://www.amazon.co.jp/dp/4861826772/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_SNX1BbN9KSA68…
10月30日
あ、ドーキンスの訳者の大田直子さんと同じく、こっちでも、兄弟でも兄弟姉妹でもなく、「きょうだい」としてあるな。
10月30日
ひらがなでひらくのはあんまりこのみではないのだけど。
11月10日
『『ゲノムで社会の謎を解く 教育・所得格差から人種問題、国家の盛衰まで』ダルトン・コンリー&ジェイソン・フレッチャー(松浦俊輔訳) 読了。
一口で紹介出来るようなら、わし学者になっておるわ。この図の意味を教えてもらっただけでもう元がとれる。線分の長さが各々の遺伝子的距離ね。 https://pic.twitter.com/mqGw3JzHfZ
11月10日
6万年ほど前にアフリカから出た1000人単位の遺伝子的ボトルネック集団の子孫(上側)が、アフリカに残った民族(一口に黒人という種族)の遺伝子的多様性に比較して、どれだけご親戚関係かという図。その他、生まれか育ちかなんて吹き飛ぶほど複雑な遺伝子と環境の相互作用を渾身で解説する傑作だよ。
![]()
『ゲノムで社会の謎を解く
教育・所得格差から人種問題、国家の盛衰まで』ダルトン・コンリー&ジェイソン・フレッチャー (松浦 俊輔 訳作品社)
『魂に息づく科学』リチャード・ドーキンス ― 2018-10-29

リラックス・ゴブさん
『魂に息づく科学──ドーキンスの反ポピュリズム宣言』リチャード・ドーキンス(大田 直子 訳 早川書房)
![]()
10月22日
ドーキンス、きっぶがいいね。江戸っ子だね。
10月29日
『魂に息づく科学:ドーキンスの反ポピュリズム宣言』ドーキンス 読了。電化書籍化寸前w これはそもそものドーキンスファン以外にはあんまり響かない気がするのだが。しかも、ドーキンスファンはデジャヴに襲われる感じ。とりあえずまずは『利己的遺伝子』から読んでくれ、と言いたくなる。
10月29日
その上で、ドーキンスファンとして言いたいのは、ピーター・シンガーばりの動物苦痛論の時には、非理性的な動物と人間の連続性を遺伝子の乗り物として強調しながら、宗教のような進化の「副作用」を理性(科学)で乗り越えようとアジるときには、人間と動物とを明確に分断していて居心地が悪い。
10月29日
それはとにかく、歳くっていよいよ理性にとりつかれた鬼のようなドーキンスとあわせて、このところ話題のジーヴスもののパロディを二編も載せて悦に入っているドーキンスも楽しめます。
チャールズ・ダーウィン『人間の由来』 ― 2018-10-20
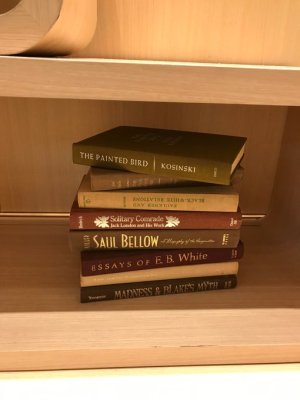
穴をあけられてインテリアにされた異端の鳥
チャールズ・ダーウィン『人間の由来』 (長谷川 眞理子 訳 講談社)
![]()
9月20日
「抽象的な言語をほとんど持たず、四より大きい数は数えられないような、オーストラリアの惨めな未開人の働きものの妻が、自意識を行使して自分の存在の性質について考察することは、ほとんどないだろう。」
ダーウィン『人間の由来』
いまでもそう思ってる輩がおる気がしてきた。
9月23日
いま読んでいる本。
『人間の由来』ダーウィン
『傭兵隊長』ペレック
『世界の行動インサイト 公共ナッジが導く政策実践』OECD
3つ目がなんか思ったほどの具体例のツッコミがないのでつらい…。でも高かったので読む。こういう宣言をすると読了できるナッジ。
10月1日
というわけで、あたしゃ、ダーウィンのヘイト本(『人間の由来』第一部)を乗り越え、第二部「性淘汰」にたどり着いた。
やっとこの年齢になってダーウィンは面白いってわかったんだよね。
教養をあえて定義するなら、面白いことが増えること、じゃなかろうか。
10月5日
ダーウィン、シミ(昆虫)には容赦ない。
「シミ目 この目のメンバーは、昆虫綱の中では下等とされている。彼らは、羽がなく、色は地味で、みっともない、ほとんど奇形のような頭とからだの形をした、小さな昆虫である。」
10月6日
ちなみに、直後で引用しているJ・ラボック卿(Sir J. Lubbock)の言葉。
「このような小さな生物がたがいに相手の気を惹こうとするさまを見るのは、たいへん楽しいものだ。雄は雌よりもずっと小さいが、雌の周りを走り、たがいにからだをぶつけあい、面と向かって立ち、
10月6日
二頭の遊び盛りの仔ヒツジのように、あとになったり先になったりして走る。しばらくすると、雌は、走り去るようなふりをし、雄は、おかしな怒ったような態度で追いかけ、雌の前に立ちはだかって対面する。雌は、恥ずかしそうにからだをそむけるが、雄は素早く雌の前に回り、触角で雌に触るようだ。
10月6日
しばらくの間、彼らは面と向かって触角で触れ合っており、まったく二匹だけの世界にいるようである」
10月8日
しかし、性淘汰を裏づける雌雄の形質の差を延々と様々な属種で列挙していく文体は、ピケティの『21世紀の資本』と同じく、どこを読んでいるのかもうここは読み終わったのではないかいつまでも終わらないのではないかなどという眩暈を起こす。
10月8日
あと、これはたぶん誤訳じゃないかな。
「擬態している方の種は、いかようにも変われるはずであるから、最終的にはそれが属しているグループの他のメンバーとはまったく異なる外見や色彩を持つことにもなるだろう。色彩にほんのわずかだけ変異が起こっても、
10月8日
多くの場合、それだけで他の保護されている種と十分に似るようになって、その変異が保存されることにはつながらないだろうから、鱗翅目の多くの種では、色彩にかなりの量の、しかも突然の変異が起こることがよくあるとつけ加えておく方がよいだろう。」
10月8日
たぶん、本来はこういう意味ではないか。
「擬態している方の種は、いかようにも変われるはずであるから、最終的にはそれが属しているグループの他のメンバーとはまったく異なる外見や色彩を持つことにもなるだろう。色彩にほんのわずかだけ変異が起こっても、
10月8日
多くの場合、それだけで他の保護されている種と『十分に似るようにはならないため、』その変異が保存されることにはつながらないだろうから、鱗翅目の多くの種では、色彩にかなりの量の、しかも突然の変異が起こることがよくあるとつけ加えておく方がよいだろう。」
それが正しいかは脇に置いて。
10月8日
もともと込み入っているので、誤訳があると擬態を見破りながら読まなきゃいかんので時間がかかる。
(私の読み間違いであればご容赦を)
10月8日
あ、いまわかった。
「擬態している方の種は、いかようにも変われるはずであるから、最終的にはそれが属しているグループの他のメンバーとはまったく異なる外見や色彩を持つことにもなるだろう。多くの場合、『色彩に起きたほんのわずかの変異だけで』
10月8日
他の保護されている種と十分に似るようになって、その変異が保存されることにはつながらないだろうから、鱗翅目の多くの種では、色彩にかなりの量の、しかも突然の変異が起こることがよくあるとつけ加えておく方がよいだろう。」
てことか。
10月8日
要は、その変異がほんの少しでも生存優位になるでなければ保存される淘汰圧はかからないから、きっと蝶の翅の色彩はけっこう一気に変わったんじゃね?という意味だけど。
10月8日
擬態がどの程度で擬態としての効果を持つかという話になると、なかなか今でも熱いそうな。
10月8日
しつこい
「多くの場合、『色彩に起きたほんのわずかの変異だけでは、』他の保護されている種と十分に似るようになって、その変異が保存されることにはつながらないだろうから、鱗翅目の多くの種では、色彩にかなりの量の、しかも突然の変異が起こることがよくあるとつけ加えておく方がよいだろう」
10月8日
けっきょく
「色彩にほんのわずかだけ変異が起こっても、多くの場合、それだけで『は』他の保護されている種と十分に似るようになって、その変異が保存されることにはつながらないだろうから、鱗翅目の多くの種では、色彩にかなりの量の、しかも突然の変異が起こることがよくあるとつけ加えて(…)」
10月10日
「ところがどっこい」、一名、わからないとのことなので。一連のリツイートで直前のある方が全否定している「アソコでアレを読む」を、アレの翻訳者その人が絶賛していて、どっちかがアレの根本的な読み方を間違えているという結論になるのだけど、そんなことこわくてアレだよ!
10月20日
やったー! 『人間の由来』ダーウィン 読了! 丸1ヶ月じゃん。いやーなんつうか。人間の由来の話なのに人間の扱いが雑きわまりないの。アリの方がずっと上。アリラブ。
10月20日
人種の話はまあ有名なのでいいとして、あれだけ「種の連続性」にこだわったダーウィンが、なして人間の祖先たちが「雄による雌の獲得競争」という性淘汰によって雌雄の形質差異を進化させたと喝破しながら、唐突に「人間は雌が雄に選ばれる」と何のひっかかりもなく言うのかというとこね。
10月20日
(人間は)雌の方が着飾るという意味で外面的にはそう見えるが本当にそうか?とか、雄が地位や名誉や財産に執着するのは…とかすっているのに、とか。もちろん、そういうとこへの反証もふくめて、その後の150年のものの考え方を決定づけてしまったという恐ろしい書であるので。アリラブ。
10月20日
最寄り駅近くの小書店がひと棚使って「人文学と科学」テーマで並べておって、これは応援しなけりゃという思いで、『魂に息づく科学:ドーキンスの反ポピュリズム宣言』を買ったのだが、早川書房じゃん! すぐに電子書籍になるじゃん! 悔しいから次読む。
『こわいもの知らずの病理学講義』仲野徹 ― 2018-06-20

絶賛爪切り中
『こわいもの知らずの病理学講義』仲野徹
![]()
6月20日
『こわいもの知らずの病理学講義』仲野徹 読了。めっちゃ売れとるで。いまも本屋で積んであった。がんを中心におっさんおばはんも(がんばれば)理解できる解説でもたぶんものすごく高度。がんが遺伝子変異を繰り返し無限に増えて死なない細胞になる病ということがよくわかりました。ええ本や。
6月20日
ほめられちった。てへぺろ。
6月30日
三月うさぎ(兄)@march_hare_bro こういう嘘がん治療にひっかからないためにも、『こわいもの知らずの病理学講義』(仲野徹)を。
『ブラインド・ウォッチメイカー』リチャード・ドーキンス ― 2018-03-25

ぼんやり
『ブラインド・ウォッチメイカー』リチャード・ドーキンス(中嶋 康裕 訳 早川書房)
![]()
2月11日
そう言えば、ドーキンスさんは『利己的遺伝子』で性淘汰についてどう言ってたっけと、自炊した第二版で検索したら、ちょっと笑った。
ゴクラクチョウの尾羽の長さについて、
「…女性のファッションやアメリカのカーデザインと同様、より長い尾羽をもつ傾向は、かくして開始され、…
2月11日
…自ずから勢いを増したのである。尾羽があまりにもグロテスクな長さに達し、ついにそのための明白な不利が性的魅力という有利さを圧倒し始めるに至って、この傾向はやっと停止したのだ。しかしこれは簡単には受け入れがたい考え方であり、ダーウィンが性淘汰という名でこの考え方を提唱して以来、
2月11日
…たえず懐疑家の注目のまととなってきた。第八章で「キツネさん、キツネさん」理論の提唱者として紹介したA・ザハヴィも性淘汰の説明を信じない一人である。彼はそれに代る説明として、*「ハンディキャップ原理」という、とてつもなくひねくれた考え方を主張しているのだ。
2月11日
(中略)
ザハヴィの理論のこの先に続く部分が非常にひっかかるのだ。ゴクラクチョウやクジャクの尾羽、シカの巨大な角などをはじめとする各種の性的に淘汰された形質は、当の持主にハンディキャップを与えているように見えるので、これまでは逆説的な存在とみなされるのが普通だった。
2月11日
…ところがザハヴィは、これらの形質は、まさにそれらがハンディキャップとなるがゆえに進化したのだと主張しているのである。長くて邪魔くさい尾羽をつけた雄鳥は、実は雌鳥に対してこんなしっぽを付けているにもかかわらずなおかつ生き残れるくらいぼくは頑強でたくましい雄なのです、
2月11日
…と宣伝しているのだというのである。」
ミラー先生が女性の化粧やアメリカのカーデザインにこだわるのは、このあたりが起源なのかしらん。
3月25日
『ブラインド・ウォッチメイカー −−自然淘汰は偶然か?−−』ドーキンス 読了。本文で木村先生の中立説には好意的なドーキンスが、創造説と同列で否定しているかのように書く日高さんもどうかと思うがまあ、とにかく目配り良くこまめにダーヴィニズムにたかるハエを潰してまわるものだなあ。
『種の起源』ダーウィン ― 2018-03-15

カメラ目線で、ごはんの催促
『種の起源』ダーウィン(渡辺 政隆 訳 光文社)
![]()
2月7日
なんか『種の起源』でダーウィンが「進化に目的はない」って言って性淘汰を否定したみたいなこと言われちゃったから、思わず『種の起源』読み始めちゃったよ。やっぱすごいなー。ほとんどの問題が対立遺伝子なんて概念もないのに出揃ってんだもんなー。
2月11日
ダーウィンのミツバチの巣の説明がわからない…。
3月15日
『種の起源』ダーウィン 渡辺政隆訳 読了。この文庫では破格に良い翻訳なのではなかろうか。よく知らないけど。わかりづらい言い回しを避けながらちゃんとくどい文章になってるところがすばらしい。もとい、遺伝子が何かわからない時代にほぼ全ての仮説と反論と予測が網羅されている。ダーウィン天才。
『予期せぬ瞬間』アトゥール・ガワンデ ― 2018-01-07

#無言でねこ写真をあげる見た人もやる
『予期せぬ瞬間 医療の不完全さは乗り越えられるか』アトゥール・ガワンデ (古屋 美登里、小田嶋 由美子 訳 石黒 達昌 監修 みすず書房)
![]()
1月7日
『予期せぬ瞬間 医療の不完全さは乗り越えられるか』アトゥール・ガワンデ 読了 凄い。
デビュー作『コード・ブルー』の復刊。
さらに、医師の意思決定に興味があれば『医師は最善を尽くしているか』を、死にゆく患者と医師の関係に揺さぶられたなら『死すべき定め』を。
https://www.msz.co.jp/book/author/16175.html
1月7日
つーわけで、ゲイリー・クライン『「洞察力」があらゆる問題を解決する』をガワンデ『予期せぬ瞬間』からの紹介で読んでる。ミスを減らす締め付けよりも見えない問題を見抜く力を伸ばす方がずっと効果的だ、という研究らしい。
![]()
『予期せぬ瞬間 医療の不完全さは乗り越えられるか』アトゥール・ガワンデ (古屋 美登里、小田嶋 由美子 訳/石黒 達昌 監修 みすず書房)
『パパは脳研究者』池谷裕二 ― 2018-01-03

ごはんは?
『パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学』池谷裕二(クレヨンハウス)
![]()
1月3日
『パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学』池谷裕二(クレヨンハウス) 読了。子供の成長を認知面から捉えて説明しつつ、マシュマロテストにうかるような子に育てようという脳科学者ならまあやるだろうことを毎月連載報告する面白エッセイ集。
1月3日
しかし、参考文献が豊富でいいのだけど翻訳があっても原論文しか教えてくれない。誰が何を参考にするのか謎。とは言え、広瀬友紀『ちいさい言語学者の冒険』とあわせて読むと微妙にパースペクティブが違って楽しい。
こういうことをするために子どもの一個くらい造っておけばよかったか。
1月3日
爆笑した脚注。P.156
「自分でやりたがる心理的傾向は「コントラフリーローディング」と呼ばれます。脳は苦労せずに得るものよりも、労働を通じて得るものに価値を感じます。例えば、ガチャガチャを回しておもちゃを取り出すのと、同じおもちゃを単にもらうのを選択させると、…」
1月3日
「…ほぼ100%の子どもが前者を選択します。この傾向はサルやイヌはもちろん、鳥類から魚類まで、(ネコ以外の)ほぼ全ての動物に見られます。(参考文献;Tarte RD. Contrafreeloading in humans. Psychol Rep 49:859-866, 1981)。」
最近のコメント